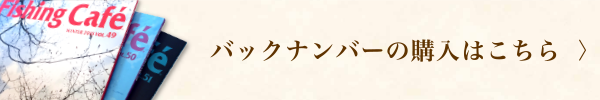04.08
南国の山と海に鍛えられた、土佐打刃物400年の技を継ぐ
粘り強い切れ味の秘密
語り◎松本志津夫
取材・文◎『Fishing Café』編集部
写真◎津留崎 健
高知竜馬空港から『松本刃物』の鍛冶工房を訪ねると、入り口近くにある炉の中はすでに朱色に染まり、耐火炉の壁越しでも近づけないほどの熱気が広がっていた。土佐打刃物の大まかな鍛冶仕事の工程は、「火造り」「荒仕上げ」「焼き入れ」「焼き戻し」「研磨」の5つ。その「火造り」の作業がすでに始まっていた。
「土佐打刃物(とさうちはもの)の特徴は、高温に熱した金属材料を丹念にたたいて伸ばし広げることによって、自由自在に形を作る『自由鍛造』です。鍛冶師(かじし)は、原寸と形を書いた注文書だけで注文品を造ることができます。したがって、用途に応じた少量多品種の製造が可能になるのです。そのかわり決まった型がないため、鍛冶師には熟練の技が求められます。また、土佐打刃物は、山林用・農業用の実用的な道具が始まりですので、切れ味だけでなく、耐久性のよさや手入れのしやすさも特徴のひとつです。主な製品には、包丁、鎌(かま)、鉈(なた)、斧(おの)、鍬(くわ)などがあります」と、南国市の数少ない土佐打刃物の伝統工芸士の一人、松本刃物2代目の松本志津夫さんは言う。
土佐打刃物の歴史は古く、高知県土佐刃物連合協同組合の資料によれば、その発祥は鎌倉時代後期にまでさかのぼり、土佐打刃物の本格的な発展と普及は、江戸時代初期、元和7(1621)年の土佐藩2代目藩主・山内忠義による「元和改革」に始まるという。
大坂夏の陣以降、土佐藩は窮迫した財政を立て直す必要に迫られ、新田開発や森林資源活用に乗り出した結果、農業・林業用打刃物の需要が増え、打刃物の生産量と品質が飛躍的に向上したのだ。このときの鍛冶師の研鑚(けんさん)が土佐打刃物を生み出したといわれている。
こうした江戸時代から続く土佐打刃物の伝統的な技術は、多少の機械化は取り入れたものの現代まで受け継がれた。そして、江戸時代初期に多くの野鍛冶職人が技を鍛えた、高知県の香美市(かみし)、南国市、土佐市、吾川郡(あがわぐん)いの町、須崎市といった、東部から中部にかけての一帯が土佐打刃物の発祥地とされ、冒頭の松本さんの説明にあるように、定められた工程で作られた刃物しか土佐打刃物を名乗ることはできない。
松本刃物は、昭和4(1929)年に松本さんの父親である正重さんが創業し、松本さんはその5年後の1934年に生まれ、小さい頃から父の後ろ姿を見て育った。鍛冶屋は家内工業のため家族で協力しなくてはならないため、松本さんが20歳の頃、家業を手伝うようになった時点で一通りの仕事はわかっていたという。
父親の正重さんの時代は、日常道具として使う刃物を注文に応じて作っており、なかでも鎌の注文が多く、南国市には鍛冶屋が十数軒あったが、どこでも鎌を作っていたそうだ。作っていた鎌の多くは、その当時日本の統治下にあった台湾へ輸出され、サトウキビなどの伐採に使われ、刃渡り30cmほどの大きな鎌もよく作っていたという。また戦時中は、鉈も軍需品のような扱いになり、この界隈の多くの鍛冶屋が鉈の発注を受けていた。最初はごく普通の形とサイズの鉈だったが、徐々に今ではあり得ないほど重く大きな鉈の注文が増えたという。現在はチェーンソーで樹木の伐採ができるが、当時この大きな鉈は、道なきジャングルを切り開くために必需だったのではないかという。
「道具は時代を映すと言いますが、最近は林業や農業の形態が変化しているので、鎌や鉈、鋤といった仕事用の刃物ではなく、レジャーで使うような趣味的なものが多くなりました。その典型が剣鉈(けんなた)です。1本あれば、釣りでもキャンプでも使え、非常に便利です。剣鉈は昔からありましたが、仕事で使う鉈の注文が減ってくるのと入れ替わりで、剣鉈の注文が増えました。秋田で使われている『マタギ鉈』のような形の注文もときどきあります」
刃物を作っていて一番難しい技術は、二つの異なる特性を持つ鋼材(こうざい)、鋼(はがね)と地金(じがね)を合わせる「わかし付け鍛接(たんせつ)」だ。松本さんほどのベテランでも、100%満足できる仕上がりになることはなかなかない。最近の若い鍛冶屋さんは、その手間を省くため、材料メーカーがあらかじめ接合した鋼材を使っていることが多いという。

水研石で刃付けの粗研ぎを行っている様子。この後、細か目(番手)のヤスリで刃先を仕上げる。刃付けが終わると平治の部分を鏡面になるように研ぎ、仕上がった製品はさび止めニスを塗り、立てて乾燥させる。乾燥が終わると最後に柄(ハンドル)を取り付ける。
「鋼と地金の分量は、作る刃物によって変わります。包丁と鉈を比較すると、鉈は刃が厚く入っているので鋼の量が増えます。単純に言えば、刃の厚みで鋼が決まってきます。うちで作っている片刃の鉈の場合、鋼が60%、鉄が40%です。両刃の剣鉈は中央の鋼が40%、両刃がそれぞれ30%ずつです。包丁は刃が薄く、スッと切るだけです。硬いものをたたいたりしないので、それほど鋼は必要ありません。斧は鉈以上に鋼の量が増えます。鋼を多く入れておければ、強い力で木を打ちつけても折れたり曲がったりしにくいのです。包丁の刃にもいろいろな厚さがあるので、目的によって鋼の量は変わってきますが、包丁で鋼を多くすると、研ぎにくくて使いにくくなります。切れ味と耐久性や手入れの良し悪しを左右するのも「わかし付け鍛接」なのです」と松本さんは話す。
松本刃物の「積層ダマスカス剣鉈」の模様は、鉄と鋼を折り返し、折り返し、何重にもなって生まれるものだ。積層にも15層、30層など種類があり、その特徴は美しい模様だけでなく、腰が強く曲がりにくいことだ。異なる素材を何層にも重ねて強さと柔軟さを出している点は、カーボン製の釣り竿も同じで、他の分野でも応用されている技術だという。
「長年刃物を作ってきてつくづく思うのは、鉈のようなシンプルな道具ほど、先人たちの長年の経験や知恵が凝縮されています。均質なものしか要求されないのであれば、私たちのような職人は、駆逐されていくのだろうと思います。『松本刃物』が存続できているのは、均質品とは違うものを求めるユーザーがいてくれるからです。とてもありがたいことだと思います」