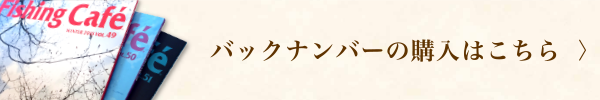09.10
― 源流での繊細な釣りとキャンプを実践するルアーアングラー ―
「ベッドより大地に直接寝るほうが、よく寝られる」
高橋雄一郎さんの野営釣行
取材・文◎本誌編集部
語り◎高橋雄一郎
写真◎知来 要
群馬県の片品川(かたしながわ)支流の河畔には、ブナとブナの原生林を伐採した後に発達した二次林のダケカンバ、ミズナラなどの落葉樹が茂り、春の訪れとともにいっせいに芽吹いていた。
大型アウトドアショップのフィッシングストアでアドバイザーを務める高橋雄一郎さんは、イワナが潜みそうなオーバーハングした淵に小型ミノーをキャストし、6フィートのルアーロッドを指揮者がタクトを扱うように繊細に操り、誘いを入れている。
ポイント選び、キャスティング、誘いの3つ動作に無駄はなく、岸際を素早く移動する足さばきはリズム感を伴い、まるで渓流で舞うヒップホップダンサーのようにも見える。
高橋さんは、群馬県高崎市出身。近くには利根川水系の一級河川・烏川が流れ、父親が生粋の渓流釣り師だったことから、物心ついた頃から竿を握っていたという。そして、渓流歩きに心配ない身長となった小学校4年生の時に、父親と群馬県みなかみ町の利根川支流に出向き、初めてイワナを釣り上げたという。
「それ以来、毎週のように週末は父と渓流へ向かうようになりました」と高橋さんは言う。
小学6年生になると、毛鉤に興味を覚えてフライフィッシングを始め、毎日タイイングとキャストの練習に励んだという。さらに中学生になると、ルアーのスピーディーさとより攻撃的な釣りの虜となり、自転車で2時間以上かけて遠征し、バス釣りに出掛けるようになったそうだ。
「高校を卒業してから自分の釣りを追求してみたいと思い、渓流ルアーに挑戦してみたのです。父が餌釣り師だったので、自分は違うアプローチで釣ってみたいという気持ちもありました。実際にやってみると、意外にも最初から釣れました。餌釣り、フライ、ルアーと一通り経験していたおかげで、魚がどこからどう出てきて、どうやって食いつくのかわかっていたからだと思います」
高橋さんの舞うような渓流ルアーフィッシングのアクションは、一朝一夕にできるようになったわけではなく、30年以上のキャリアのたまものだ。高橋さんはその日、朝から4時間ほどの釣りで28㎝を筆頭に10匹近いイワナを釣り上げリリースし、キャンプ地へと向かった。

今回利用した 「皇海山(すかいさん)キャンプフォレスト」は、皇海山の麓、標高800mに位置する林間キャンプ場。自然の高低差を利用した場内は、「小さな森の秘密基地」をコンセプトに多くのキャンパーたちに親しまれている。片品川からも近く、フィッシングキャンプのベース基地にはうってつけの場所。
www.sukaisan.com/index.html
今回のキャンプ地は取材スタッフの人数も考え、釣り場の近くで眺めのよいキャンプ場を利用した。到着すると高橋さんは、まず一人用のウイングタープを張り、その下にグランドシートを広げ、必要な道具を車から降ろす。次に焚き火台を設え、持参した薪に火を入れて火床が安定するまでの間にテントを張り、マットとスリーピングマットを広げて、テントのジッパーをしっかり閉める。その一連の作業も釣りと同じく無駄がなく、まるで自分の庭でキャンプをするかのように、わずかな時間で設営を終える。そして、ジュラルミンボックスから調理器具やランタンなど、キャンプに必要な道具を取り出し、ジュラルミンボックスを調理台にして夕食の準備を始める。
「キャンプを教えてくれたのも父です。夏休みになると必ず、父と遠征釣行に出てキャンプをしていました。今は一人で源流泊をすることが多いですね。静かな山中で寝袋にくるまって寝ると、家のベッドより熟睡できます(笑)。キャンプ自体も楽しいのですが、僕にとってはあくまで、日をまたいで釣りをするための手段のひとつです」

高橋さんがキャンプをした時によく作る、モッツァレラチーズのベーコン巻き焼き。簡単だがおいしく、食べ応えがある。
タコとセロリの炒め物に山菜の「こごみ」を加えてみた。シャキッとした食感と豊かな風味が、さらに食欲をそそる。
春の山菜は川辺で採取することもできるし、道すがらの売店で買うこともできる。
渓流釣りは、夏は夜明け前の暁から、山間から薄日が差すまでの早朝が勝負だ。その後はどんなテクニックを駆使しても、夕方まで全く反応がない場合もある。そんなときは午前10時前にキャンプ地に戻りブランチを済ませ、「夕方まで木立の下で昼寝」とのんびり過ごすこともあるそうだ。
「キャンプを前提とした釣りは、帰宅を気にせず魚の捕食時間に合わせて釣りができるので、その結果釣果も上がり、メリハリのある釣行が楽しめます。そこが魅力ですね」
はぜる焚き火を眺めながら高橋さんは、フィッシングキャンプの魅力を語ってくれた。