11.10
「釣りは人生の“ライフタイム・ギャランティ”」より
アウトドアの道具と一緒に輸入した自然文化
文◎遠藤 昇 写真◎知来 要
40年ほど前、自然の営みを学ぶために、衣・食・住を背負って心の赴くままに人跡未踏のウィルダネスへ分け入る、バックパッキングというアウトドアスタイルを道具と共に直輸入したのが赤津孝夫氏だ。
「バックパックを背負い、ときにはフィッシングロッドを手に自然に感謝し敬いながら、知恵・知識と道具を駆使してサバイバルするアウトドアの体験は、いつの時代になっても人にとって根源的に必要なアクティビティです」と、赤津さんは言う。
一本のナイフ、そして一本のフィッシングロッドがあれば、より多くの人がグレートアウトドアに親しみ、自然の叡智を学ぶことができるというのだ。
*
今回その赤津さんのインタビューと撮影を行ったのは、山梨県・忍野からの湧水を含む多くの流れが相模湖に注ぐ桂川。愛犬とともにやってきた赤津さんは、開口一番「この川は相模湖があるため、来るたびにハプニングがあるんです」と言う。
相模湖は巨ベラ(50㎝前後の個体)釣りや冬のワカサギ、ブラックバスなど、首都圏から気軽に出かけられる釣り場として有名だが、イワナやヤマメ、レインボートラウトやブラウントラウトなども、相模湖と桂川を行き来しながら自然繁殖している。特にブラウントラウトは、平均水深19mほどの相模湖の環境下で、寿命を延ばし大型化する個体が多い。赤津さんはここで、幾度もそうしたトラウト系魚種に一喜一憂させられた経験があると言う。
「今日は釣れても釣れなくても、このデカいウルフで行こうかと思って」と赤津さんは、今シーズン最初に使うフライを嬉しそうにティペットに結んでいる。
ウルフパターンとは、もともとメイフライ・イミテーションとして考案されたフライで 浮力があり、視認性の良さを兼ね備えている。盛夏以降の源流のイワナ釣りに利用することが多いが、辺りが暗くなるイブニングライズ、流れの中に大石や小石などが多く起伏に富んだ川の釣り上がりに適しているフライだ。
周囲を見回すと、確かに小型のメイフライ(カゲロウ)が水面を叩き、時折上空をゆらゆらと舞っている。そのカゲロウたちを散らすように、赤津さんの豪快なキャスティングが始まった。インタビュー前にまずは、一匹釣りましょうというのだ。
*
本誌57号に詳しく記しているが、赤津さんは長野県の松本平で自然を相手に釣りや野遊びを楽しみ、幼少・少年期を過ごした。その後、写真家を志望し、日本大学芸術学部写真学科に入学。大学の同級生で親友に一ノ瀬泰三さんという報道カメラマンがおり、卒業後も親交が続いていたが、当時はベトナム戦争が激化していた。クメールルージュがカンボジアを支配し、アンコールワットを破壊していたが、親友はそれを単独で撮影しようと潜入し、最後に赤津さん宛の手紙に「地雷を踏んだらサヨウナラ」というメッセージを書き残して消息を絶ったのだという。戦場カメラマン・一ノ瀬泰三氏の「地雷を踏んだらサヨウナラ」という言葉は有名だが、まさかその手紙の受取人が赤津さんだったことには驚いた。
その頃、赤津さんはフランスの『ELLE』誌で正式に採用された日本人カメラマン吉田
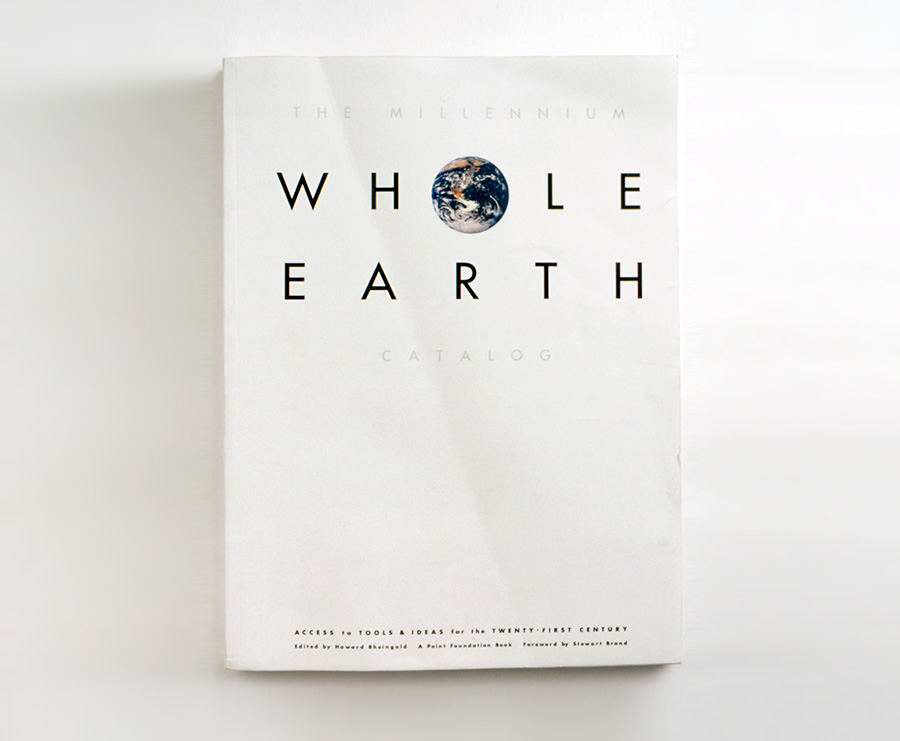
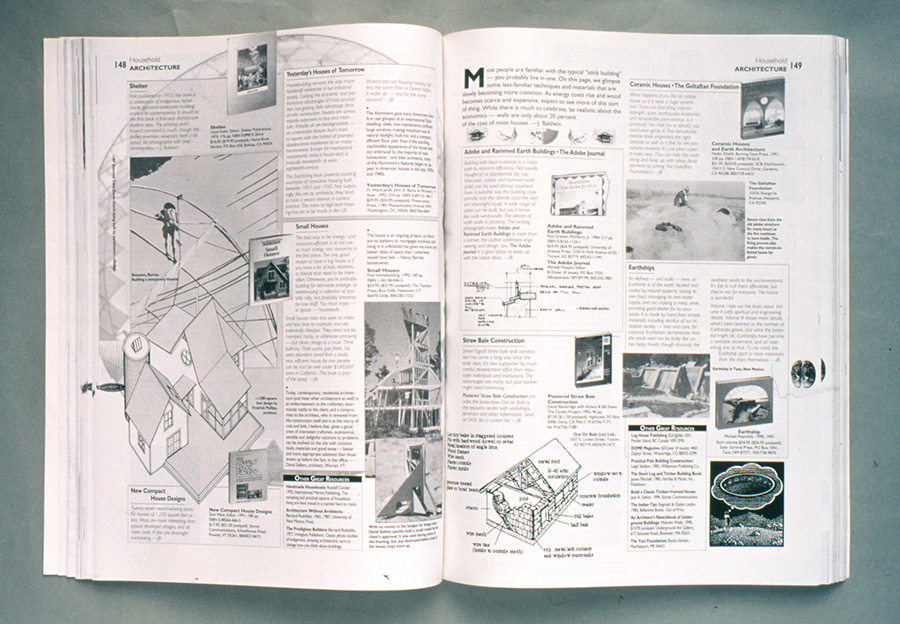
1968年、スチュワート・ブランドという当時29歳の若者が、創刊したカタログ雑誌が『WHOLE EATH CATALOG』。“Access to Tools”というコンセプトで自然回帰を唱えていたアメリカの若者の間でベストセラーとなり、社会に大きな波紋を投げかけた。後にアップルコンピューターを作ったスティーブ・ジョブスもスチュワートから多大な影響を受けた。
「その頃よく通っていたのは、ダイビング用品とハンティング用品を扱うショップで『輸入・販売業は面白そうだな』と思うようになり、それがこの仕事を始めるきっかけのひとつでした。ちょうど1973年頃ですね」と赤津さんは言う。
当時アメリカでは、「車から家まで、大きくて重くて、ゴージャスに見える装飾」を良いとするアメリカ文化を否定するカウンターカルチャーが、若者を中心に広がりを見せていた。そのシンプルな生き方の代表として、“バックパッキング”というアウトドア文化が支持され始めていたのだ。バックパッキングは、野外で必要な道具のすべてを背負っていくために「モア・レス」と言う考え方が根底にある。そして、自然の中で生きるためのアクセスを可能にする道具カタログとして、『ホールアースカタログ』が出版され、若者の間でベストセラーとなった。また、アウトドアウエアもゴアテックス、シンサレート、ダウン、シンチラ、60/40のような新しい素材が採用された革新的な時代だった。
そのなかで赤津さんは、アメリカの新しいアウトドア・アクティビティを自ら体験し、その技術や精神を広めるために、アウトドア用品の輸入販売を行う会社を設立した。
忙しい日々の中で赤津さんにとって釣りは、特別な意味を持っていたという。なかでも、幼少期の釣りとは別次元に自身を運んでくれたのが、フライフィッシングだった。
「午後3時に仕事を切り上げて車を飛ばし、養沢で夕まづめの釣りに通うほど夢中になりました」
“養沢”とは、『養沢毛鉤専用釣場』のことだ。アメリカ人の法律家でありGHQの法務部に所属していたトーマス・レスター・ブレークモア氏(1915―1994年)が、東京都のあきる野市にある養沢川の清らかな流れに惚れ込み、故郷オクラホマで親しんだフライフィッシングを楽しむために、自己資金で川を借り上げて魚を放流し、毛鉤専用の釣り場を開業したのが始まりとされる。
その養沢に通うなかで、「フライフィッシングは、魚を釣るためだけの釣りじゃない。魚をとりまく生態系を理解するためのものでもある」と理解し、さらに熱中したと言う。
「今、思うと“魚をとりまく生態系を理解する”ことは、魚を釣るための最短の知識なんですよね。それはフライフィッシングだけではなく、どんな釣りでも言えることです。たまたまフライフィッシングは、仕掛けも道具立てもシンプルだから、どうしてもそういった知識が大きなウエイトを占めたわけです」
釣りは、自然にアクセスできないと成り立たない遊びだ。それは逆に自然を知るための、最も身近な方法でもある。動物を知って山を知り、魚を知って川や海を知る……。知れば知るほど、自然を大切にしなければいけないと思うようになったと言う。
*
赤津さんの放ったフライが、二つの瀬が交わる淵の際に落ち、ゆっくりと流れに乗る。ドラグが掛かるギリギリまでフライを流し、ピックアップする。それを2回ほど繰り返して3回目、やや上流にフライを落とした瞬間だった。小さく水面が割れ、飛び出したのは20cmほどの綺麗なヤマメだった。魚に触れることなくリリースした赤津さんは、岩の上に腰かけて「あのサイズなら、今年は産卵活動に参加できますね」と嬉しそうに話す。そして、バックパックを手前に寄せてストーブでコーヒーを沸かし、ポケットから1本のフォールディング・ナイフを取り出してチーズを切り出した。

バックパッキングには、モア・レス(何を削るか)と言う考え方が根底にある。フライフィッシングもその考えが当てはまる。この二つのアウトドア・アクティビティは、自分にとって生きるための大きな指針になったと、赤津さんは言う。
「このナイフは『BUCK KNIVES』という、僕の会社が黎明期の時代から扱っている商品のひとつです。このメーカーがすごいのは、当時から“ライフタイム・ギャランティ”、つまり生涯保障という考え方で物づくりが行われていたことです。大量生産が主流となり、使い捨ての文化が始まっている当時にしては画期的ですよね。買った人の要求にメーカー側が応えているのです。『良い物だけを持ちなさい、大切にしなさい』という考えです。今、ヤマメを釣って思ったのですが、この日本で釣りをすることは、その人の人生にとって言うなれば“ライフタイム・ギャランティ”を得たことに他ならないと思います。人生を楽しむための生涯保障です」
日本は、国土は狭いが自然は豊かで、変化に富んでいる。南にはサンゴ礁の海があり、北には流氷が流れてくる海がある。黒潮があり、サケが遡上する川もある。屋久島に行けば、三千年も四千年も生きている杉がある。しかも、東京からわずかの時間で、こんな綺麗なヤマメとも出会える。そういう国は、世界中を見渡してもそうそうない。この素晴らしい環境で釣りをするためにも、やはり自然を身近に感じ大切にしなければならないと、赤津さんは言う。
赤津孝夫(あかつ たかお)
1947年長野県生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業。幼少時より父親の影響で、釣りや狩猟などを通して四季の山野に親しむ。1970年代初頭、日本にフライフィッシングとバックパッキングを紹介した芦澤一洋氏と出会い、エコロジーに根ざしたアウトドアスポーツの必要性を感じ、1977年にアウトドア用品の輸入販売会社「エイ アンド エフ」を創立。また、サバイバル術にも熟達しており、さまざまなワークショップでも活躍。著書に『スポーツナイフ大研究』(講談社)、『アウトドア200の常識』(ソニー マガジンズ)、『アウトドアサバイバルテクニック』(地球丸)など多数。











