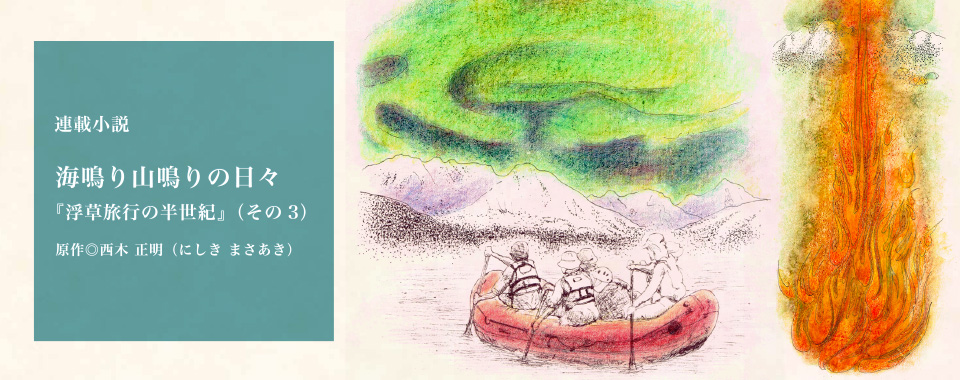海鳴り山鳴りの日々
『浮草旅行の半世紀』』(その3)「フロートキャプテン」
西木正明
「それは大変だ。日程的に無理だと思うよ」
わたしたちが行こうとしているアラスカ北西部の北極圏を、東西に横断する形で聳える、ブルックス山脈の山裾一帯。日本全土をそのまま呑み込んでしまうほどの、広大な荒野である。
そこを仕事場にしているブッシュパイロット、リンカーン・アクスラックは、イヌピアック系のネイティブエスキモーで、この界隈で屈指のパイロットとして知られている。
そのリンカーンに、今回の川下りは日程的に無理だと思うと言われた。にわかフロートキャプテンのわたしは、かたずをのんでそのやりとりを聞いている、ガイドのジム・リパインたちテレビクルーの顔を見やって言った。
「聞いての通り、日程的に無理だとさ。あと一日か二日、延長できるかな」
ディレクターのトビー・グッドマンが、すぐさま首を横に振った。
「いや、オンエア予定日から逆算して、これ以上取材に費やす時間はない」
「では巨大イワナがいるキリー川は諦めて、別の川にするか」
「それはもっと困る。今回はABCネット経由で、アメリカ全土で放送されることを前提としたコンテンツ作りだ。三〇インチ(約七六センチ)オーバーの巨大イワナというウリがないと、インパクトが半減して、放送自体が危うくなる」
「ならば、川を下る距離を短くしても駄目かね。具体的には、出発点を当初の予定より数十キロ下流にする」
パイロットが、元義弟の親友ということもあって、わたしはその場で思いついた妥協案を示した。リンカーンは顔をしかめて、首を横に振った。
「キリー川の下流には、本流のノアタック川との合流点以外、飛行機が降ろせるような川原がない」
われわれが目指すキリー川は、全長一〇〇キロ程度の川で、ブルックス山脈の中腹を水源とする。
流域には人家がゼロで、文字通りの原始河川だ。野生動物の聖域で、アークティックウルフ(北極オオカミ)やグリズリー(アラスカヒグマ)、ムース(ヘラジカ)、カリブー(トナカイ)などと、たやすく遭遇できる場所として知られている。
大物狙いのハンターたちにとっては、まさにパラダイスとも言われる地域だが、問題がひとつある。現場に辿りつくのに不可欠の、ブッシュプレーン(小型飛行機)が発着可能な場所を見つけるのが大変なのだ。
「とりわけ下流は川の蛇行が激しく、滑走路として使えるような、直線で障害物が少ない川原がそうそうないんだ」
パイロットのリンカーンはそう言って、下る距離を短くして日程を短縮しようという、わたしの提案を一蹴した。
だが、わたしは諦めなかった。この時点まででも、アラスカの川を十数本下っている。同じ川を繰り返し下り、その都度川の様相が激変していることも経験していた。
そうした経験や記憶からすれば、下流にだって滑走路向きの川原のひとつやふたつ、見つかるに違いないと思いこんでいたのだ。
「わかった。ではこうしよう。今われわれは二泊三日の予定で、大イワナ釣りを撮影しながら川を下ることを前提にして、話をしている。たとえば下る距離を二〇マイル(約三二キロ)ほど上流側に延ばして、二泊三日で下ることにすれば、滑走路として使える川原が見つけやすくなるのではないか」
わたしのこの提案に、ディレクターのトビーが複雑な表情で問い返して来た。
「要するに三泊四日で下る距離を、二泊三日で下る。そうすれば多少上流の、滑走路に適した川原がある所から川下りを始められる。そういうことだな」
「そのとおりだが、ディレクターの君に、多少お願いがある」
「どんなことだ?」
「二泊三日の前半は、どんどんすっ飛ばして下る。そして後半はねちっこくポイントを丁寧に攻めながら下る。こうして前半は魚影を確認する程度にして、後半でカットを稼ぐ」
「ピックアップポイントは、ノアタック川との合流点だったな。つまり前半はすっ飛ばして撮影もそこそこにして、下流の取材でカットを稼ぐということか」
わたしは無言のままうなずいた。
ディレクターが呆れ顔で言う。
「取材の旅という趣旨からして、それは本末転倒ではないかな」
「たぶんキリー川の上流には、魚がほとんどいない。そんな所で時間を食ってもしょうがない。だからどんどん飛ばして下る。下流ほど釣れる魚が大きくなるはずだから、番組の仕上がりを考慮しても、そのほうがいい」
ジム・リパインがおもしろそうに茶々を入れてきた。
「フロートキャプテン、まるで地元のエスキモーのような託宣だが、上流でガンガン釣れてもすっ飛ばして下るのか。下流が空っぽの川だったらどうする」
「ガンガン釣れたら、すっ飛ばしてもカットは稼げる。要は番組がきちんと作れればいいんだろ」
ディレクターが禿げ頭をつるりと撫で、にやりと笑って言った。
「あなたの言っていることが、なんとなく理解できた。それで行きましょう。ミスター・アクスラック、今の話のようなことでいいですかね」
「こっちの仕事は、あんたらを現場まで安全にお連れし、安全に連れ戻すだけだ」
翌日午前五時。
わたしたちは二機のセスナ180に分乗して、コッツビュー空港を飛び立った。小一時間ほどの飛行で、眼下にのたうつ大河ノアタック、前方にはブルックス山脈が、紫色の蜃気楼のような佇まいで聳え立っている場所に達した。
日米合わせて総勢十人という大所帯な上、川下りの必需品であるラフトを三隻、パドルを二組、テント大小合わせて三張り、寝袋やマットを十人分。ほかに米やパン、野菜などを、二機の小型機につめこんでいる。
こんな満タン状態の飛行機を、見知らぬ奥地の川原に降ろせるのか。
わたしはメインパイロットが元身内の相棒という特権で、リンカーンが操縦する機体の副操縦席に陣取って、あれこれ話しながら飛んだ。
「当初の予定より二〇マイル(約三二キロ)ほど上流に降りたいとのことだけど、その手前にランディングできそうな川原があったらどうする?」
離陸して間もなく、意外ともいえる質問をリンカーンが投げかけてきた。
「それはもう、ぜひそこに降りてほしい」
前夜打合せの場で、自分のささやかな経験をもとにして、行ったこともないのにキリー川の上流部は魚影が薄い、だからすっ飛ばして下流に賭けようなどと、断定的に言った。もとより確信があってのことではない。だから、できることなら川が細くて浅い、上流部での釣りは避けたい。
リンカーンのいうように、少しでも下流に降りることができて、実際に下る距離も短くなれば、日程的にも楽になる。
前夜酒の勢いで言ったことを、翌朝後悔する。そんな気色の悪さを味わいながら、重ねてパイロットに言った。
「一〇マイル(約一六キロ)程度下流でも、取材用の時間がうんと増える。だからできるだけ下流から出発したい」
「ではやってみよう。しかしそこは、わたし自身も未経験の場所なので、うまく降りられるかどうかは保証できないよ」
腕っこきのパイロットらしからぬせりふを吐きながら、リンカーンは淡々とセスナを操っている。
やがて広大な濁流の本流、ノアタック川に左手から合流してくる、青く澄んだ流れの上空に達した。
「キリー川だ。左岸の川原が滑走路だよ。いったんここに着陸します」
合流点上空で旋回し、眼下の川原を見据えながら、リンカーンが言った。
「ここから先は、あなたとわたしだけで偵察飛行を行ない、安全に着陸できる川原を見つけてから、ほかのお客さんと荷物を運ぶ」
そう言いながらリンカーンは、ノアタック本流の上空で機体を斜めにして旋回し、高度五〇メートルぐらいまで降下したところで、無造作に合流点脇の川原めざして突っ込んで行った。
意外なほどなめらかに着陸し、そのまま二〇〇メートルほど滑走して停止した。
「では、あなた以外の方はいったんここで降りてもらい、しばらくお待ちいただく。われわれの機体からは荷物も降ろす」
そう言ってジム・リパイン以下のテレビクルーと、友人の歯医者夫妻および妻、釣友、そして荷物のすべてを下ろして、リンカーンとわたしだけを乗せた一機だけで発進した。
あっという間の早業に、ただただ驚いていたわたしも、飛行機が上空で水平飛行になったところで、この先どうするかを知りたくなった。
機種を北に向け、蛇行するキリー川の流れをなぞるようにして飛び始めを確認してから、被っていたヘッドセットを外してリンカーンに問いかけた。
「これからどうするんだ」
「十五分ほどキリー川沿いに飛んだところで、着陸可能な川原を探します。見つかったら着陸し、あなたを降ろします。その後自分は、先程の合流点まで引き返し、待っている皆さんと荷物を乗せて戻ってきます。そこから先は、あなたが決めることです」
はあ、そうかいと思いはしたものの、事態をよく理解しないまま、周囲の光景に目を凝らした。フロートキャプテンのもっとも大切な任務のひとつに、その時点で自分たちがどこにいるかを、正確に把握することがある。まだGPSなどという文明の利器が普及する以前の話だ。川沿いは完璧な無人地帯で、川には道標などない。
頼れるのはFAA(連邦航空局)発行の航空地図と正確なコンパスだけ。蛇行を繰り返す川の上で、現在地を正確に把握するには、このふたつをフルに使いこなすことが大前提となる。
加えて、地図に記載された地形を把握し、周囲に聳える山を灯台代わりにして、現在地を特定すること。いわゆる山だてが、無人の荒野を流れる川を安全に下る、絶対条件になる。
ほかにも川下りの現場で必要な知識もあるが、それはおおむねフロートキャプテンまかせで大丈夫だ。
「おっ、もしかしてあの川原、使えるかな」
リンカーンの声でわれに返った。
「ほら、あれだ。降下してチェックするからよろしく頼みます」
前方でキリー川が大きくカーブしていて、その右岸側にかなりの広がりをもつ川原が横たわっている。
「約七〇〇フィート(約二一三メートル)程度の平らな直線が取れる。長さは十分だが、問題は石ころと灌木だ」
そうひとりごちながら、リンカーンは機体をどんどん降下させて、下流側から川原めざして突っ込んで行った。あと数百メートルほどのところで、リンカーンが言った。
「あ、グリズリーだ。あいつ、ランディングを邪魔しなければいいがな」
「えっ?」
わたしは驚いて、機首前方の川原に目を凝らした。
「いた!」 対岸に聳える河岸段丘の日陰になって、上空からは見えにくかった川原の水辺に、大型のアラスカヒグマが立ちこんでいる。
「たぶん岸際の浅瀬に魚が寄っている。それを狙ってるんだ」
パイロットはそんなことを言いながら機体を降下させ、やがて下流側から、高度五〇メートルほどの低空飛行で、川原上空に突っ込んで行った。その間視線は、機首前方の川原に張り付けたままだ。ひとつでも大きな石や流木が転がっていると、着陸時につんのめったり、横転したりする事故につながる。
川原上空をほんの数秒間で通過して、いっきに高度をあげた。
「どうだった? たぶん大丈夫だと思うが」
「うん、たぶんね」
通過した時の速度は、約五〇ノット(約九三キロ)程度という失速ぎりぎりの低速だったので、かなり細かく観察できた。そのかぎりにおいては、大きな石や流木という障害物はなかったように思う。
問題はそこかしこに生えている、ドロヤナギなどの灌木だが、蹴散らせるだろう。
「よし、ここにしよう」
リンカーンはそう言って機体を旋回させ、今度は着陸を前提として、再度下流側から突っ込んで行った。
ふと、あのグリズリーはどうする、と聞きたくなった。その時、あたかも当方の懸念を察知していたかのように、水から上がった巨大なグリズリーが、全身から水滴をまき散らしながら、川原左手の藪に向かって突進しているのが目に飛び込んできた。
「あいつ、あぶねえことをしやがる。ぶつかったらどうするんだ」
リンカーンは大声でそう言いながら操縦桿をわずかに手前に引き、機首を持ち上げた。やがてエンジン音が低くなり、機体は着地寸前の状態になった。
直後、大きな衝撃があり、続いて荒れたごろた石の上を走る時に特有の振動が、機体をはげしく震わせた。やがて機体が停止し、リンカーンが得意そうな笑顔で言った。
「オーケー、ここで大丈夫だ」
エンジンを止め、シートベルトを外す。機外に降り立ち、周囲を眺めながら奴が言った。
「では、わたしはノアタック合流点まで戻って、お客さんと荷物を運んでくる。その間あなたは、滑走路上の障害になりそうな石と流木を除去してくれませんか。そしてこれ」
奴はそう言って機体後部のドアを開け、アックス(手斧)一振りと、トイレットペーパー一巻きをつかみ出した。
「滑走路上に生えている灌木を根本から抜き取ってください。そしてその灌木の幹に裂け目を造り、このティッシュペーパーを適当な長さに切って巻き込み、アネモスコープ(風向計)を作って、滑走路両端に立てて下さい。ではよろしくお願いします」
「ちょ、ちょっと待ってくれ。あのグリズリーはどうする?」
「ああ、あれでしたら大丈夫です。さっき上空から見た時、そこのブッシュの先に広がるツンドラに、何頭かのオオカミが群れをなしていました。グリズリーはオオカミが大嫌いですから、戻ってこないと思います。では、一時間以内に戻ってきますから」
冗談じゃないよ。
そう言いたくなったが、こういう時はパイロットのひと言は天の声である。
(続く)