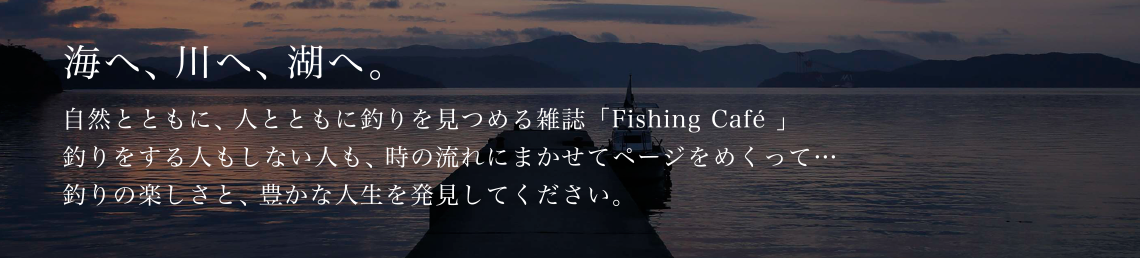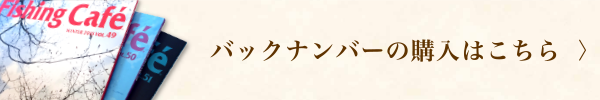WINTER 2026 VOL.82
コイ釣りと鯉文化、身近な巨魚との深いつながり
コイを学ぶ、鯉で憩う
コイ釣りと鯉文化、身近な巨魚との深いつながり
コイを学ぶ、鯉で憩う
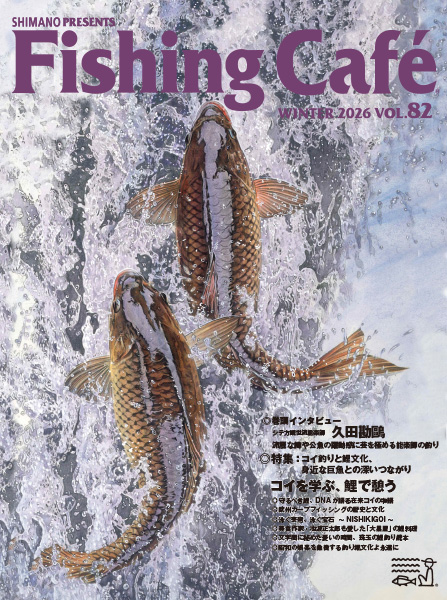
- 3
シテ方観世流能楽師
久田勘鷗
流麗な鱒や公魚の躍動感に芸を極める能楽師の釣り - 11
コイ釣りと鯉文化、身近な巨魚との深いつながり
コイを学ぶ、鯉で憩う
- 13 ◎ 守るべき鯉、DNAが語る在来コイの物語
- 17 ◎ 欧州カープフィッシングの歴史と文化
- 23 ◎ 泳ぐ芸術、泳ぐ宝石 ~NISHIKIGOI~
- 27 ◎ 美食作家・池波正太郎も愛した「大黒屋」の鯉料理
- 31 ◎ 文字間に秘めた憂いの時間、珠玉の鯉釣り読本
- 34 ◎ 昭和の娯楽を象徴する釣り堀文化よ永遠に
◎ 巻頭インタビュー
◎ 特集
● 連載コラム
- 35 ● 太公望万歳! − [元プロ野球選手・監督 川上哲治]
- 37 ● 『釣・魚画帖』入門 − 宮田亮平
- 39 ● 釣人たちの輪舞曲 − 錦織則政
- 43 ● 釣音 − 宮沢和史
- 48 ● 町田成一の美味礼賛 − 「炭火割烹 蔓ききょう」
- 53 ● 釣りとの遭遇 − 福岡伸一
- 57 ● 魚と人 − [インディーズフィッシュの有効利用]
- 60 ● Magical Aquarium Tour − 猿渡敏郎
- 64 ● 【釣具物語】釣具、漁具の歴史とその変貌
- 68 ● Fishing Café CLUB
NEXT ISSUE VOL.83 2026年 4月 発行
「釣りを深く知る“私の釣魚読本”」
The Complete Guide of The Best Books on Fishing
― 行間に揺れる活字からの魚信 ―
水辺で釣り糸を垂らす期待感や好奇心が釣りの楽しみのひとつなら、書斎やリビングで好みのお酒を少しずつ嗜みながら、釣り関連書物の活字を追い、写真集や見知らぬ魚の図鑑を眺めるのも、かけがえのない時間です。そんな“アームチェア・アングラー”や釣りに興味を覚えはじめた方たちのために、釣り文学の雄として有名なヘミングウェイや開高健、往年の釣り師たちに多くのエールを送った井伏鱒二や高橋治。そして、昭和初期に『釣魚大全』として全12巻におよぶ実用書を執筆した上田尚など、釣りや釣り旅の魅力に迫った名作を厳選し、釣りを深く、広く知る釣り読本の世界へ案内します。
フィッシングカフェ取り扱い店舗
※五十音順
Fishing Shop フナヤ
福井店
FISHINGヒカリ
アカサカ釣具(株)
アメリカ屋漁具
イーハトーヴ釣具店
エース
オオツ釣具
かみやまつり具店
かめや釣具
岡山平井店
佐世保大塔店
サファ福山西店
下松店
総本店
鳥取店
長崎諫早店
長崎時津店
長崎戸町店
名古屋みなと店
福岡原店
松江店
宮崎店
米子店
コルソ札幌
佐々木銃砲釣具店
シマヤ釣具
木更津店
上州屋
アウトドアワールドつきみ野店
我孫子店
池袋店
牛久店
川口店
川越店
川崎東口店
坂戸店
草加店
つくば店
土浦店
長野川中島店
松戸常盤平店
三郷店
三鷹東八店
谷和原店
ジャイアント
草加店
(有)玉屋釣具店
つり吉
江戸川店
つり具センター
旭川店
屯田店
西岡店
伏古店
つりぐの岡林
戸次店
高城店
釣具の三平
上町店
土佐道路店
釣り具の天狗堂
安城店
岡崎大樹寺店
岡崎光ヶ丘店
高浜店
知立店
豊田本館
豊田ルアー館
西尾店
つり具のブンブン
LINKS UMEDA店
厚木店
大津店
柏店
岐阜店
京都伏見店
埼玉狭山店
堺店
相模原店
高井田店
高槻店
奈良郡山店
西昆陽店
ルアルア あべの店
ルアルア ルアルアくずはモール店
釣具のポイント
伊川谷店
諫早長野店
出雲店
大分高城店
岡山西バイパス店
鹿児島谷山店
熊本インター店
熊本富合店
久留米津福バイパス店
高松国分寺店
千葉蘇我店
徳島藍住店
徳島小松島店
鳥栖商工団地店
西広島バイパス店
八幡本店
八幡本店 LureStadium
播磨店
姫路店
福岡花畑本店
福山蔵王店
松山平田店
宮崎恒久店
姪浜店
山口小郡店
横浜港南台店
横浜都筑店
米子皆生店
釣具のまつお
つり具のまるきん
糸島店
伊万里本店
佐賀北部バイパス店
つり具のマルニシ
つり具のヨコオ
久留米店
本店
釣具のわたなべ
平井店
釣りのマルハン
つりよし釣具店
東海つり具
ナチュラム
長谷川釣具店
フィッシャーズ
黒埼店
金沢店
上越店
竹尾I.C店
富山店
福井店
村上店
フィッシャーマン釣具館
イチバンエイトグループ
エイト2
エイト3
アネックス
エイト大阪南
エイト京都伏見
エイト本店
エイト玉津
1BAN梅田
イチバン池田
フィッシング相模屋
フィッシングジョーズ
フィッシングハウス キヤ
フィッシングマックス
芦屋店
泉大津店
上野芝店
岸和田店
神戸ハーバー店
三宮店
なんば店
武庫川店
和歌山インター店
(有)ブルーマリン
プロショップオオツカ
川越水上公園店
プロショップ カサハラ
プロショップかつき
プロショップMOGI
プロフィッシャー・システムズナカシマ
へら竿のときわ
マニアックス
みなとや釣具店
ヨシダ釣具店
新宮店
宗像店
ルアーフライショップ上飯田